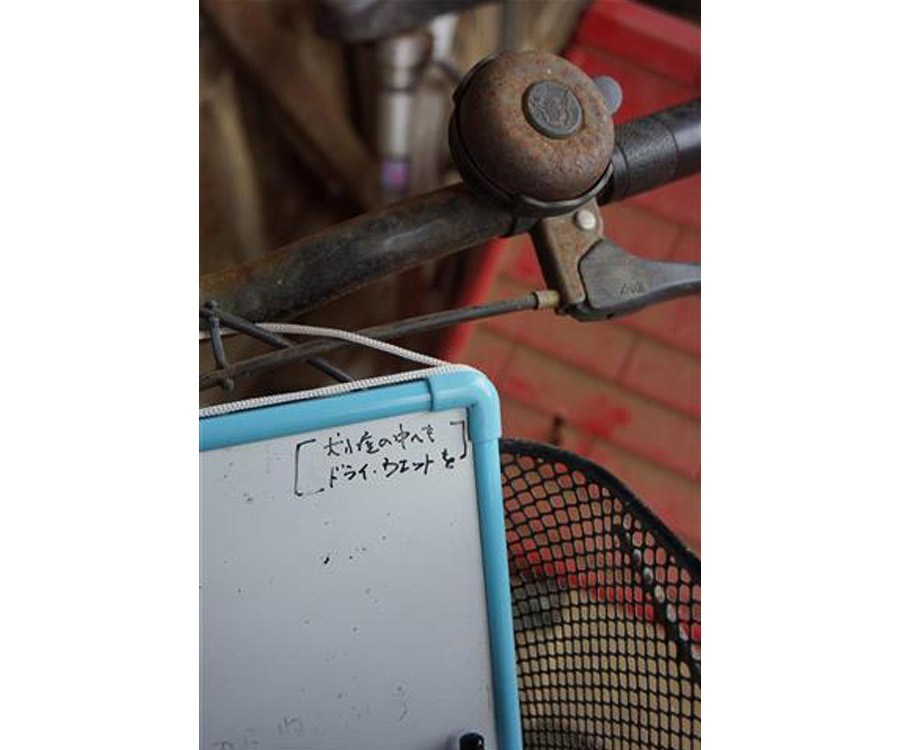【再掲記事】飯館村ワンニャン給餌ボランティア|東日本大震災、震災後の記事を振り返る
東日本大震災から11年。次の大震災に備えて、この経験をしっかり覚えておくために、「くるくら」では震災3年後の被災地の状況を伝えた記事を再掲することにしました。4回目は「飯館村ワンニャン給餌ボランティア」です。
この記事をシェア
本記事は2014年2月に「メイトパーク」(「くるくら」の元サイト)に掲載した内容の再掲です。現状を伝える記事ではありませんのでご注意ください。
犬は、人の姿を見ると飛び出してくることが多いが、このワンちゃんは怯えているのか竹藪に隠れた。
被災地に残された命をつなぐボランティア
東日本大震災に端を発した福島第一原発の事故後、原発から20余kmに位置する福島県飯館村は計画的避難区域に指定され、全村民が村外へ避難しなければならなくなった。そして、避難期限の1か月後、住民がいなくなった村に残されたのは飼い犬と飼い猫だった。もちろん、残したくて残したわけではない。同村の避難先は動物の飼育が禁止のため、やむなく残すしかなかったのである。飼い主にとって、それがどれくらい辛いことであったかは、想像に難くない。
最初の1年間で、命を落とした動物たちは少なくなかったようだ。日中の帰宅は許されているが、高齢化が進んでいることもあり、すべての飼い主が毎日食料をやりに帰村できるわけではない。せめて飢えないよう、飼い主は大量の食料を置いていくが、自然豊かな同村はたぬきや猿、野鳥など野生の動物も多く、食べられてしまうことも多い。住民がいなくなったことで、野生の動物たちもまた飢えて食べ物を探しているのだ。冬の寒さも厳しい。氷点下になると、水が氷って飲むことさえできなくなる。この地域の多くの犬は、番犬として外飼いに慣らされているとはいえ、それでも厳しい環境。まして体力で劣る飼い猫には、単独では生きていくのが難しい状況と言える。

食べ物を置いてしばらく隠れていたら子猫が顔をだした。犬と違って猫はなかなか姿を現さない。給餌作業中に出てくれば、美味しいウェットフードを食べることができるのだが……。
人なつっこいだけに、孤独な環境におかれた犬の寂しさは相当らしい。日比さんが顔を出すと、よろこぶ、よろこぶ。
それでも、動物たちの多くは、今も頑張って生き続けている。その命をつないでいるのが給餌ボランティアの人たちだ。「僕らが行くことで、助けられる命があるんです」と言うのは、福島県郡山市に住む給餌ボランティアの日比輝雄さん。日比さんは、食料や水、清掃道具などを車に満載し、ときには一人で、ときには奥さまの優子さんと一緒に、ほぼ毎日飯館村に通い続けている。往復の走行距離は200kmを越えるといい、この長距離の運転が何よりも大変だそうだ。
給餌ボランティアとして日比さんが行うのは、村内に残された飼い犬、飼い猫を訪れ食料と水を補給し、健康状態を確認し、時には散歩をさせて、必要であれば小屋周りの掃除を行うことだ。また、これ以上、不幸な動物たちを増やさないよう去勢・避妊処置も手伝う。猫の通り道などに捕獲用の網を置いておき、処置の終わっていない猫がかかると獣医師のもとへつれていき、翌日同じ場所に放す。さらに、帰村中の住民の人と会えば、ボランティア作業の承諾をもらったり、最近の犬や猫たちの様子を伝えて情報交換を行う。村の人たちとのコミュニケーションは、このボランティアに欠かせない仕事のひとつだ。ちなみに、住民の人に不在時の給餌活動の承諾を訪ねると、ほぼ全ての人が快く承諾してくれるという。
毎日は来られないので、ドライフードを大量においていく。野生のたぬきや猿、ねずみなどが狙うので、いろいろ工夫はしているものの、それでも食べられるという。
犬を、複数飼っている家もある。ひとりぼっちよりは良いかもしれない。
避妊/去勢手術につれて行くためには猫を捕まえる必要がある。そのための捕獲器。なかなか捕まらない猫もいるが、避妊/去勢は徹底しないと意味がない。
阪神大震災の経験をきっかけに
広い村内で、犬と猫が残されている場所は200か所を越えるそうだ。日比さんはすべての場所を確認し、覚えているという。ただ、一日に回れるのは多くても30か所のため、本当にボランティアを必要としている動物たちを助けられるよう、常に優先順位を考えているという。現在、ほぼ毎日通っているのは日比さんだけだが、定期的に通っている給餌ボランティアが十数グループあり、最近は、日比さんと連絡をとりあうことで効率が上がっているという。

外の様子を窺う猫。犬よりも小さく弱い猫は、野生動物との争いでも不利。そのせいか、怯えた雰囲気の猫も多かった。
それでもフードがあると、空腹なのか、周りを警戒しながら顔をだす。
日比さんが現れると、尻尾をプロペラのように回して大喜び。しかし、1か所に長くは滞在できない。帰るときの追いすがってくる顔を見るのがつらいという。
日比さんが給餌ボランティアを始めたきっかけは、自身が阪神大震災の被災者であり、その際にペットの救済が必要なことを痛感し、また実際にボランティアに助けられたからだ。飯館村で給餌ボランティアを始めた当時、日比さんはまだ神戸在住。月に約2回、電車で通い、現地でレンタカーを借り、すでに給餌ボランティアを行っている人たちに話を聞きながら、活動したという。その後、通いでは費用も時間もかさむこと、仕事が定年を迎えたタイミングもあり、一昨年の8月に、45年間暮らした神戸を離れて移住を決意。郡山で家を探し、奥さまと愛犬とともに移り住んだ。
郡山へ移ってからは、インターネットでの情報発信も積極的に始めた。その成果で、それまで単独で活動していた給餌ボランティアのグループに横のつながりができた。また、ネットを見て、ボランティアに参加したり、フード等の支援も集まるようになったという。多くのボランティアは、東京周辺などから夜中に車で移動し、早朝から一日飯館村で活動を行う。女性も多い。本当に大変な活動だ。そのような中で、日比さんの自宅は、現地でのオアシスのような役目も果たしている。
他のボランティアも活動しているため、給餌状況のメモを残すこともある。
犬を思って小屋に毛布が入れられていることも多いが、毛布は濡れると乾きにくく、冬は氷ることもあるため、毎日通えないところでは、毛布は外しておくという。
原発事故前の飯館村は、春から秋には花に満たされる村だった。山と谷が緩やかに続く風景は高原を思わせるが、海にも近いという恵まれた場所。また、多くが開拓地のため、村民の村に対する愛着も強い。しかし今は、多くの場所で放射線量計が3マイクロシーベルト/時という高い値を示す。春になると、無人の村に花だけが咲き乱れる。そんな村を毎日駆け巡りながら、「僕も若くないんだけど、あと5年か10年か、犬や猫たちが天寿をまっとうするまでは、彼らの命をつないでやりたい。原発を作った世代の責任ですかね」と、日比さんは穏やかに言う。
飯舘村内で、他のボランティアと合流することもよくある。一休みしたり、情報交換をしたりと貴重な時間だ。
取材協力=飯館村ワンニャン給餌ボランティア
●震災から11年、取材当時を振り返って
屋根裏でカメラを構え静かに待っていると、そっと顔を出した猫(2枚目の写真)。僕に気づいて、すぐに引っ込むかと思ったが、しばらくじっとこちらを見ていた。鳴くこともなく、鳴いても猫語は分からないが、「私達のことも忘れないで伝えて」という声がしっかり聞こえた。
取材を行ったのは震災から3年後。まだまだ大変な状況に置かれている人たちがたくさんいる中で、放置された愛犬、愛猫の給餌ボランティアの情報を聞いた。まだ援助が必要な人がたくさんいる時期にどうしてペットなのかと思いつつも、一方で興味を持ち、同行取材をさせてもらった。
一緒に村を周って分かったのは、人のいない村に放置され、給餌ボランティアを心待ちにしている犬や猫たちがたくさんいること。そして、やむを得ず愛犬や愛猫を置き去りにするしかなかった飼い主の気持ちと、ボランティアに対する感謝だ。もちろん、ボランティアがいかに大変かも。
家族同様であったペットへの思いは、人に対するものに近い。しかし、動物だということで、弱者だということで、ある意味切り捨てられてしまった。それは仕方ないことではあったが、弱者を切り捨てたという現実があったこと、またそれを助けようという努力があったことは、伝えなければいけないと取材を通じて強く感じた。今後も大震災は、間違いなく起こるだろう。その際には、弱者にもできる限りの助けの手が及ぶようにしなければならない。