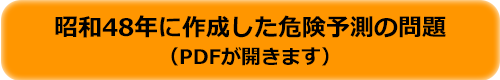ミラー越しにドライバーの目線を感知?|長山先生の「危険予知」よもやま話 第35回
JAF Mate誌の「危険予知」を監修されていた大阪大学名誉教授の長山先生からお聞きした、本誌では紹介できなかった事故事例や脱線ネタを紹介するこのコーナー。今回は「危険予知」と「危険予測」という2つの用語の存在理由と『JAF Mate』では「危険予知」が採用された経緯、さらに本誌の危険予知が教習所のカリキュラムと運転免許試験に影響を与えたことなどを話していただきました。
この記事をシェア
ミラー越しにドライバーの目線を感知?
編集部:今回は右側を走っていたトラックが、右折待ちをしている車を避けてこちらにはみ出してくるケースです。並走していると、自分の車が相手の死角に入っている危険性がありますね。相手が大型トラックだと、より死角が大きいので危険ですね。

片側2車線ある幹線道路の左車線を走っています。右側の車線は交通量が多くなっています。

右側のトラックが進路変更してきて接触しそうになりました。
長山先生:そうですね。パネルトラックは側方がほとんど直視できないので、死角が大きくなりますね。自分と関係しそうな車や人の行動を予測することは「危険予知」でとても大切なことですので、相手の運転者が自分に気づいているかどうかの情報が重要になります。
編集部:でも、並走している状態では相手がこちらに気づいているかどうか、まったく分かりませんね。
長山先生:たしかにトラックの左側を走っているのですから、運転者の顔は見えず、こちらに気づいているのかどうか判断できません。唯一、手がかりがあるとすれば、トラックの大きなサイドミラーを通して見える運転者の目線です。
編集部:ミラーを通して見える運転者の目線ですか? 見えますかね~?
長山先生:ミラーの大きさや向き、車内の明るさなど条件がよくないと難しいですが、ミラーを見ているかどうかは顔の向きで確認できると思います。ミラーを通して運転者の目線を感知して、相手がどのような行動をとるか推察するようにします。
編集部:それが「危険予知」なのですね。ところで、本誌ではずっと「危険予知」ですが、安全運転の講習や一部テキストでは「危険予測」とも言われています。意味的には同じかと思いますが、使い分ける理由があるのでしょうか?
長山先生:おっしゃるとおり、「危険予知」と「危険予測」という言葉が混合して使われているので、不思議な感じを持っている人が多いのではないでしょうか? 実は私もその一人で、どうしてなのか考えてみました。
厚労省は「危険予知」、警察庁は「危険予測」
長山先生:結論から言いますと、「危険予知」と「危険予測」は同じ意味で使われています。ただし、厚生労働省及び国土交通省関連機関では「危険予知」を、警察庁及び文部科学省関連機関では「危険予測」を用いています。労働省(現厚生労働省)で先に「危険予知」という用語を使っていたので、警察庁ではその言葉でなく「危険予測」という用語を使うことになったと思われます。JAFの主務官庁は警察庁ですから、「危険予測」が使われて当然と思われますが、「危険予測」が使用される前から『JAF Mate』では「危険予知」と言う用語を使用していたので、現在でもそのまま使われているのでしょう。
編集部:なるほど。そもそも「危険予知」「危険予測」はいつから使われ始めた用語なのですか?
長山先生:まず、危険予知・危険予測という言葉が使われるかなり前、約半世紀前に私は「危険感受性」という言葉を使っていました。私が運転免許を取る頃は「安全・危険」という観念もほとんどありませんでした。第33回のよもやま話でお話ししましたが、私は運転免許を取得して直後に危うく事故になる経験をしたことで「判断母型」と「認知母型」の概念形成をし、それと同時に「危険」「安全」を強く意識するようになりました。
編集部:危険予知が使われる前の半世紀前ですか!? 「危険」という概念がなかったというのは意外ですね。
長山先生:私が運転免許を取得した昭和33年では、交通関連の法律は道路交通取締令に基づいていて、そこには「危険」という言葉は以下の4箇所でしか使われていませんでした。①危険防止のため交さ点、トンネル、橋等に一時停止をする以外は……、②投石、投球等の危険な行為をする、③交通が希疎で危険の虞(おそれ)のない道路、④物を運搬する場合、飛散、漏出、転落、刺傷等の危険を防止。つまり、運転者の立場でどのような対象・状況が危険で、それをどのように感受するかという考え方はまだ生まれてなかったのです。「安全」という概念も、明確化されたのは昭和35年に道路交通取締令から道路交通法に変わり、第70条に(安全運転の義務)が取り入れられてからです。
編集部:「危険」や「安全」という言葉は、使い方が決まっている用語だったのが、能動的に判断する用語になったような感じですね。でも、「危険感受性」という言葉を使うきっかけになった理由はあるのですか?
長山先生:日本運送株式会社という運送会社の運転手の「危険感受度」を調べて、事故の起こし方とどう関係するかを明らかにする研究を行ったことがきっかけです。
職業ドライバーの危険感受度をテスト
編集部:どんな方法で危険感受度を調べたのですか?
長山先生:16㎜フィルムで動画撮影した15の運転時の危険場面を見せて、どの程度危険だと思うか回答してもらう「危険感受性テスト」を行ったのです。その研究結果を昭和39年(1964年)に広島大学で行われた日本心理学会で発表しましたが、それが日本で最初に動画を用いた「危険予知」に関連するテスト結果の研究発表だったと言えます。その後の研究としては、運転者は危険を感知していても大して危険でないと判断すると、その危険をあえて取ろうとする傾向が認められるため、「リスクテイキング(Risk-taking)」の研究を続けて行ったものです。
編集部:「危険を取ろうとする」の取るは、除去(回避)ではなく、冒すほうですね。
長山先生:そうです。Risk-takingと言う用語がリスクを取るということですので「取る」と言えるわけです。安全運転のためには危険を予知することが何よりも大切ですが、事故を起こす可能性がある危険を知りながら危険な行動を取ってしまうことは許されないことです。例えば、追い越しをする場合、対向車が来ていて少し危ないと思いながら追い越しをしてしまうことがあります。急いだり、焦ったりする心の状態ではそのような傾向が現れるわけです。
編集部:慎重な人の行動を「石橋を叩いて渡る」と言いますけど、リスクを取るかどうかは、その人の性格によっても違いますよね。
長山先生:そのとおり、性格的にリスクをとる傾向のある人(Risk-taker)もいますし、危険に気づけばそれをやっては危ないとリスクを避ける傾向のある人(Risk-avoider)もいます。各種場面の動画を用いて長距離運転手のリスクを取る傾向を測定した結果、無事故運転手はリスクを取ることを避けようとする傾向があり、事故多発者はリスクを取る傾向が明らかになりました。また、若い年齢の運転手はリスクを取りやすい傾向があり、また扶養者の有無でみると、扶養者がいない独身の運転手はリスク傾向が高く、妻・子供を扶養する運転手はリスクを取る傾向が低いことが明らかになりました。
編集部:なるほど。よく「結婚して家族ができたら、スピードを出さなくなった」という話を聞きますが、実際にそれが裏付けられたのですね。話は変わりますけど、「危険予知」は交通安全だけでなく、労災関係の講習やテキストにも使われているようですね。
長山先生:おっしゃるとおり、労働災害を防止するため、工場などで危険予知訓練(KYK)が行われています。これは海外の交通安全教育用のシートをヒントに作成したようです。
編集部:海外の交通安全教育用のテキストですか? じゃ、交通安全のほうが労災より早く「危険予知」の考え方を導入したのですね。
長山先生:ベルギーのソルベイ社が実施していた交通安全教育用のシートをヒントに、工場での労働災害防止用にKYK(危険予知訓練の略語)が誕生したと言われています。昭和48年(1973年)に労働省関係の事業所を中心とした「中央労働災害防止協会」が設立され、そこの「欧米安全衛生視察団」に参加した住友金属工業和歌山製鉄所の労務部長が考えたそうです。昭和48年(1973年)と言えば、私は大阪府の安全運転管理者講習で、「見ることの重要性」をテーマに危険予知・予測に該当する講義を行った年でした。参考まで、その講義で用いた危険予知の写真を紹介しましょう。初期のKYKの教材は簡単な線画のイラストでしたが、私たちが作成・使用したものは写真で運転時の危険を表現したもので、現実性のあるものでした。今から考えると、半世紀ほど前に現在の教材と変わらないものを利用し始めていたのです。
編集部:同じ年に安全運転管理者用の交通安全教育テキストと工場労働者用の「危険予知」の考え方が発表されたのですね。昭和40年代とはかなり昔ですね。
長山先生:そうですね。昭和40年代に「危険予知」のベースはできていましたが、現在のように運転免許の学科試験に「危険予測」という新しい用語が取り入れられたのはかなりあとで、平成10年(1998年)のことでした。
運転免許試験に「危険予測」が採用される
編集部:平成10年(1998年)でしたか? 『JAF Mate』の「危険予知」が平成3年(1991年)に始まったので、それより7年後だったのですね。
長山先生:平成6年(1994年)、警察庁交通局において「学科試験の在り方に関する調査研究委員会」が発足し、それが契機となって、運転免許試験に「危険予測」が取り入れられることになったのですが、その調査研究委員会が発足した由縁として『JAF Mate』が大きな意味を持っていたのです。平成3年(1991年)から連載している「危険予知」はJAF会員に非常に好評で、会員の方々が自分の所属する中学・高校、事業所、そして自動車教習所などで問題・結果写真をそのまま利用したり、自分たちで問題を作成するなどして、交通安全活動の上で幅広く活用されていたからです。また、調査委員会の委員長だった私と副委員長だった科学警察研究所の村田交通部長の二人ともドイツの運転免許試験に関心が深く、それが頭にあって意見を交わしたことも影響したと言えます。
編集部:ドイツの運転免許試験ですか? 以前見せてもらったことがある交通場面を写真で見せるものですね。
長山先生:そうです。ドイツの試験に関しては、約1000問の運転免許試験問題が公表されており、それを掲載したテキストを書店で購入し、自分で学習することができる方式になっていました。私も村田交通部長も、その試験問題が道路交通における運転時の危険とそれを防御する方策を学習するうえで非常に効果が高いという共通の認識を持っていました。そんなドイツの試験問題の存在と、『JAF Mate』の「危険予知」の人気もあって、警察庁は「危険予測」を運転免許試験にも取り入れていく必要性を認識したと言っていいでしょう。もちろん、諸外国において運転免許試験・運転者教育に以前から採用されていたことも契機になったことは言うまでもありませんが。
編集部:長山先生が委員長を務められていたとはいえ、『JAF Mate』の「危険予知」が運転免許の試験問題に影響を与えたなら凄いことで、嬉しい限りですね。
長山先生:そうですね。「危険予測」の導入が決まってからは、各都道府県警察本部の運転免許課の担当者を警察学校に数か月入校させ、試験問題の作成など実施に向けた準備が着々と行われました。ちなみに、平成10年には運転免許試験に「危険予測」の問題が取り入れられましたが、あらかじめそれに先立って自動車教習所の学科教習と技能教習のカリキュラムの中に危険予測が取り入れられたのです。
『JAF Mate』誌 2018年2・3月号掲載の「危険予知」を基にした「よもやま話」です。
記事の画像ギャラリーを見る