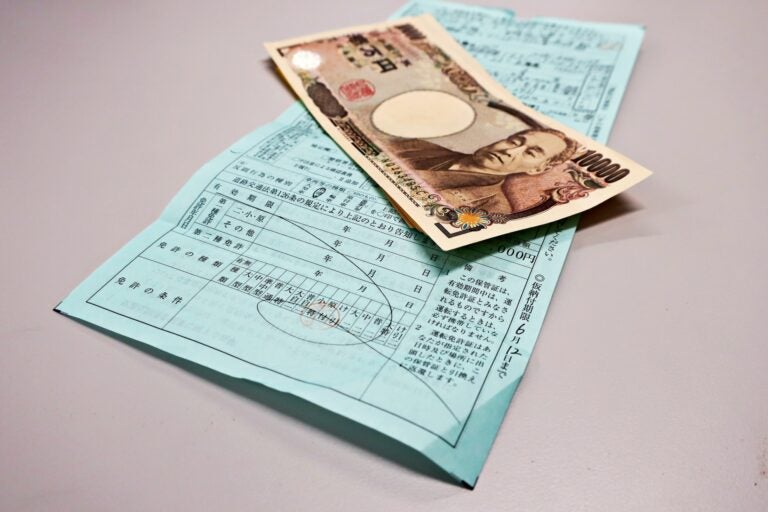自転車で走行中、信号は歩行者用と車両用どちらに従う? ~弁護士に訊いてみた~【クルマと法律vol.11】
交通問題やクルマに関する相談について、法律の見地から分かりやすく解説する連載「クルマと法律」。今回は、自転車を運転しているときの交通ルール。自転車で走行中に、歩行者用と車両用のどちらの信号に従うべきかを弁護士・芳仲美恵子先生に聞きました。
この記事をシェア
「自転車に乗って横断歩道を通行するときの信号は、歩行者用と車両用のどちらに従うべきですか?」
※本記事では、普段の生活で多くの方が利用する自転車は、ほぼ、道交法施行規則9条の2の2以下で定められている車体の大きさや構造の基準を満たす「普通自転車(道交法63条の3)」であると仮定。「普通自転車」を単に「自転車」と記載しています。
自転車で横断歩道を通行中、どの信号に従う?
相談者:前回(クルマと法律vol.10)は、自転車に乗ったまま、「横断歩道」を通行していいのかを相談しました。そこで、例外的に「歩道」通行を許されている自転車が「横断歩道」を通行する場合があることを教えていただきました。それでは、そのような自転車が「横断歩道」を通行するとき、どの信号に従うべきなのでしょうか。
芳仲弁護士:自転車が「横断歩道」を通行する場合、従うべき信号は、歩行者用信号です。
相談者:歩行者用なのですね! どうしてそうなるのでしょうか?
芳仲弁護士:まず前提として、道路を通行する「車両」は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなくてはなりません(道交法7条)。そして、信号機の表示する信号の意味や、信号機について必要な事項は、政令で定めるとされていて(道交法4条4項)、それを受けて、道交法施行令2条において公安委員会が設置する「信号の種類」と「信号の意味」が細かく定められています。
相談者:信号の種類と意味ですか。考えたこともありませんでした。
芳仲弁護士:その信号について定めた政令のうち、いわゆる「歩行者用信号(人の形の信号を有する青色・赤色灯火)」については、「歩行者」にとっての意味だけでなく、「自転車」にとっての意味が以下の通り定められているのです(施行令2条1項)。
【いわゆる歩行者信号の意味】
人の形の信号を有する青色灯火:自転車は、横断歩道において直進をし又は左折することができること
人の形の信号を有する青色灯火点滅:横断歩道を進行しようとする自転車は道路の横断を始めてはならないこと
人の形の信号を有する赤色灯火:横断歩道を進行しようとする自転車は道路の横断を始めてはならないこと
これらの規定から、「横断歩道」を自転車が通行する場合は、いわゆる「歩行者用信号」に従うべきことが定められていると考えられるのです。
相談者:人の形の信号の中に、自転車にとっての意味も定められていたのですね。では、自転車が「自転車横断帯」を走行する場合(道交法63条の6)もやはり、「歩行者用信号」でいいのですか?
弁護士:車両用信号ではないという意味ではその通りですね。厳密にいうと「歩行者・自転車専用」信号に従う必要があるということです。つまり施行令2条4項、道交法施行規則3条の2第2項によって「歩行者・自転車専用」と表示された信号機が設置された場合、自転車は、この信号灯火の意味するところに従って通行するということが定められています。実際、自転車横断帯の設置されているところは、ほぼ例外なく「歩行者・自転車専用」と表示された信号が設置されています。

(c)Imaging L– stock.adobe.com
自転車横断帯は見かけなくなった?

(c)ramustagram– stock.adobe.com
相談者:そういえば、自転車横断帯って見かけなくなったような気がします。最近は、車道路面上に青い帯状の自転車専用通行帯(自転車専用レーン)や、青色矢羽根型路面標示(青色矢羽根)、自転車のピクトグラムが描かれているのをよく見かけます。
芳仲弁護士:そうですね。実は、自転車横断帯は横断歩道に接して設けられる例がほとんどだったのですが、自転車横断帯があると、かえって危険であるという指摘がされていました。例えば、「車道」を走行してきて交差点を直進進行しようとする自転車は、「自転車横断帯」を通行するために、いったん左折するかのような挙動を取り、その直後、直進方向へと再度方向転換をする挙動を強いられます。短時間内に2度にわたり方向転換をする、この自転車の挙動が危険を招くという指摘です。
他方、レジャーや健康指向を踏まえて自転車の効用が見直されたり、配達用の自転車が増加したりして、自転車利用者が増加。それに比例して、歩道上を走行する自転車による悲惨な事故も社会問題化しました。
相談者:確かに、ニュースなどでもそういった報道を見ましたね。
芳仲弁護士:そのような危険があるとはいえ、 特に都市部では自転車専用道路(道路法48条の13)を広く設置することも困難です。そこで、「自転車は車道通行が大原則」という考えのもと、道路や交通状況に応じた自転車通行空間の整備を促進するための方策を検討。平成28年7月に国土交通省道路局と警察庁交通局が「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を策定しました。
その中で限られた道路空間をどのように安全に利用するかが広く検討された結果、道交法で車道通行する自転車の例外として定められている「自転車横断帯」は、実際上ほぼ消え失せてしまったのです。
相談者:そんな事情があったのですね。
芳仲弁護士:現在、「自転車横断帯」は、交差点の直前まで歩道と隣接して「自転車専用通行帯」が設けられているような場所や横断歩道橋の下といった場所に限定されてきています。
相談者:まだ残っている場所もあるのですね。

左)交差点の直前まで歩道と隣接して「自転車専用通行帯」が設けられている場所。 右)横断歩道橋の下に設けられた自転車横断帯。 (c)Google
自転車で車道を通行するときの信号は?

(c)Caito– stock.adobe.com
相談者:ちなみに、車道の左側端を通行していた自転車が交差点を通過するときは、「車両用信号」に従えばいいのですか?
芳仲弁護士:はい、その通りです。
相談者:そうすると、自転車の交通ルールは、以下のような整理で間違いないでしょうか。
(1)自転車は、車道の左側端を走行するのが原則である。
(2)車道の左側端を走行してきた自転車は、交差点では、いたずらに進路変更することなく、「車両用信号」に従って交差点内を直進走行する。
(3)歩道通行を許された自転車が歩道を走行してきたときは、横断歩道を通行するのがよい。
(4)横断歩道を通行する自転車は、「歩行者用信号」に従う。
芳仲弁護士:そのとおりですね。なお、例外的に許されて歩道を通行している自転車が、充分に安全を確認したうえで車道左側端に出て、「車両用信号」に従って交差点内の車道を走行することは、それだけで直ちに違法とは断言できません。
しかし、例えば、進行方向の「歩行者用信号」が青色点滅を開始したとき、「車両用信号」がまだ青色灯火であるのを発見。早く交差点を通過するために「車両用信号」に従おうとして、急いで車道に飛び出すといったような運転は極めて危険です。そのような場合、安全運転義務違反(道交法70条)のほか、具体的事情次第でそれ以外にもさまざまな交通法規に違反する可能性が高いのでしないようにしましょう。
相談者:わかりました。いかにも交通事故の原因となりそうな危険な走行ですね。絶対にしないようにします。
青色矢羽根や自転車マークはどんな意味?

(c)mtdk– stock.adobe.com
質問者:ところで、先ほど話に出た、「青色矢羽根」のペイントや自転車のピクトグラムは、道交法上の道路標示としての意味はあるのですか?
芳仲弁護士:道路標識等の種類、様式、設置場所、その他道路標識等について必要な事項は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令。以下「道路標識令」)」という内閣府令・国土交通省令で定められています(道交法4条5項)。
自転車専用レーンとして、車道の左側端付近の路面に青い帯のうえに「自転車専用通行帯」という文字がペイントされているケースは、道路標識令に定めがあります。さらに、道交法上も、公安委員会が道路標識によって指定した車両通行帯(道交法20条2項)と位置づけられているため、自転車以外の車両の走行はできません。よって、実際に取り締まるかどうかは別として、自転車以外の車両が走行した場合、道交法上の「通行区分違反」の対象になりえます。時間帯によって設けられる「バス専用レーン」では、実際に取り締まりがされています。
質問者:自転車専用であると法律で定められているレーンもあるのですね!
芳仲弁護士:はい。他方、「青色矢羽根」のように、道路標識令に規定されていない単なる「路面表示」でしかないものもあります。このようないわゆる「法定外表示」は道交法上の「道路標示」にはあたりません。そのため、例えば、青色矢羽根の上を自転車以外の車両が走行しても、通行区分違反にはなりません。
しかし、青色矢羽根は、道交法上のルールに沿って、自転車が走行すべき正しい位置と方向を明示するものです。矢羽根の形状から逆走を抑制できたり、周囲の車両から幅寄せされにくくしたりといったメリットも多いものです。
質問者:確かに、青色矢羽根があったほうが自転車で車道を走りやすいと感じますね。
芳仲弁護士:ちなみに、道交法上の取締対象か否かとは別に、例えば、交通事故が起きたときに民事上の「損害賠償請求額」を決定するにあたって、相互の過失割合を判断する上では、法律(道交法)上の義務違反の有無や程度だけではなく、実際の交通ルールとしての「法定外表示」を遵守していたか否かも、無影響とはいえないでしょう。
質問者:「法定外表示」とはいえ、守らないのはおかしいですよね。
芳仲弁護士:そうですね。自転車は車道通行が原則ですが、特に大都市では、幼児や高齢者に限らず「自転車通行可」とされている「歩道」が多いのが実情です。しかし、自転車に乗って「歩道」を通行する以上は、歩行者の安全に充分に配慮しましょう。さらに、「横断歩道」を通行する場合も「歩行者用信号」に従って、安全な通行を心掛けねばなりません。また、「自動車」と混在しながら「車道」を走行する場合には、「車両用信号」に従い、周囲の交通状況にも充分に配慮して安全運転を心掛けることが重要です。
質問者:はい。充分に気をつけて運転しようと思います! ありがとうございました。
———————————————————————————————————————
(公財)日弁連交通事故相談センターでは、電話による交通事故無料法律相談を実施しています。
TEL:0120-078325 平日10:00~16:30(第5週を除く水曜は19:00まで延長)
https://n-tacc.or.jp
———————————————————————————————————————