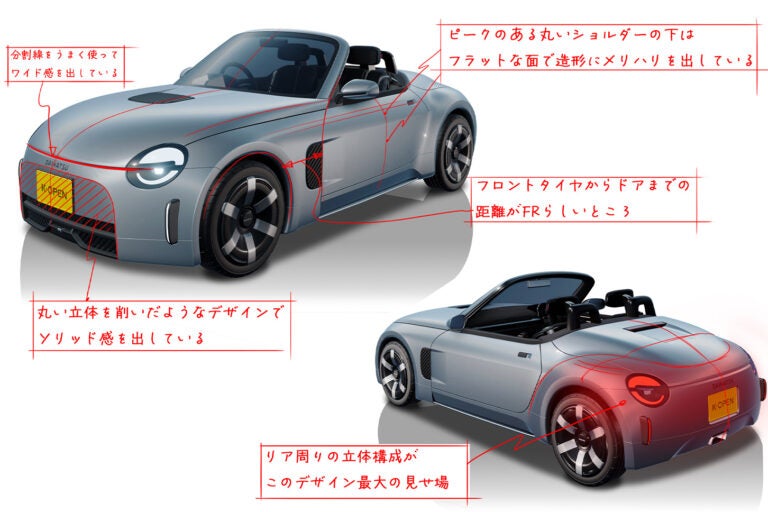ゼブラゾーンを走ると交通違反になる? 駐停車はOK? そのルールや注意点を解説。
交差点の手前などでよく見かける白い斜線模様「ゼブラゾーン」。その上を走行しているクルマを見かけることがありますが、違反にならないのでしょうか? そのルールや注意点について解説します。
この記事をシェア
ゼブラゾーンは「安全かつ円滑な走行」を誘導するためのもの

ゼブラゾーンは、車線が減少する箇所や合流地点・分岐地点に設置されています。
クルマを運転していると、道路上にある白い斜線が引かれたエリア「ゼブラゾーン」を目にすることがあります。道路が混雑しているときに、このエリアに進入してしまうこともありますが、道路交通法違反にはならないのでしょうか?
ゼブラゾーンの正式名称は「導流帯(どうりゅうたい)」といいます。道路標識、区画線及び道路表示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)に基づき、車両の走行を安全かつスムーズに誘導する目的で設けられています。
設置場所は、主に交差点の手前や車線の分岐・合流部、複雑な形状の道路など。とくに右折レーンや左折レーンが現れる直前の位置に多く見られます。
これは、交通の流れを整理し、ドライバーに進行方向をわかりやすく示すためのものであり、あくまで「誘導目的」の表示とされています。
ゼブラゾーンを走っても違反にはならないが、リスクは高い

ゼブラゾーンを走行することは推奨されていません。地域によっては独自の制限がされている場合も。
ゼブラゾーンは、「交通の方法に関する教則」によると「車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分」とされています。教習所などでも安全な走行の誘導を目的としている区間として、このゼブラゾーンにむやみに進入しないよう指導するのが一般的です。
しかしゼブラゾーンは、道交法第17条6項で「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない」と定められている「安全地帯」「立入禁止場所」ではないため、ゼブラゾーンを走行しただけで、道交法上の違反行為になるわけではありません。
また、一部の地域では、より明確な規制が定められていることもあります。例えば宮城県では県独自の交通規則により、「ペイントによる道路標示の上にみだりに車輪をかけて、車両(牛馬を除く。)を運転しないこと」と定めており、ペイント部分に車輪をかける行為を原則として禁止しています。「みだりに」とあるため、ゼブラゾーンを走ると絶対に違反になるという訳ではありませんが、宮城県内を走行する際は、普段よりも注意する必要があるでしょう。
原則「入らない」。ただし緊急時などはやむを得ないケースも

進入しても違反ではないが、交通事故のリスクがある。
前述のように、ゼブラゾーンは、車両の通行を推奨していないエリアであるため、道路が混雑しているときにうっかり進入してしまった場合、思わぬ招くおそれがあります。
例えば、交通が混雑している状況で右折レーンに進入するとき、ゼブラゾーンに進入して直進しようとする車両とゼブラゾーンを避けて右折レーンに入ろうとする車両が交錯してしまい、交通事故が起こるおそれがあります。
もちろんゼブラゾーンで駐停車することも極めて危険です。道路交通法で駐停車を明確に禁じているわけではありませんが、ゼブラゾーン上にクルマを停めると、後続車との追突事故や交通の妨げになるおそれがあります。
また、ゼブラゾーンで停止していた車両と他の車両が接触した場合、「本来進入する必要のないエリアにいた」として、当事者に不利な判断がされることもあるため注意が必要です。
このように、ゼブラゾーンは通行禁止エリアではありませんが、走行も駐停車も基本的に避けるべきエリアです。あくまで安全かつ円滑な走行のために設けられたスペースであることを理解し、やむを得ない場合を除き立ち入らないようにしましょう。
記事の画像ギャラリーを見る