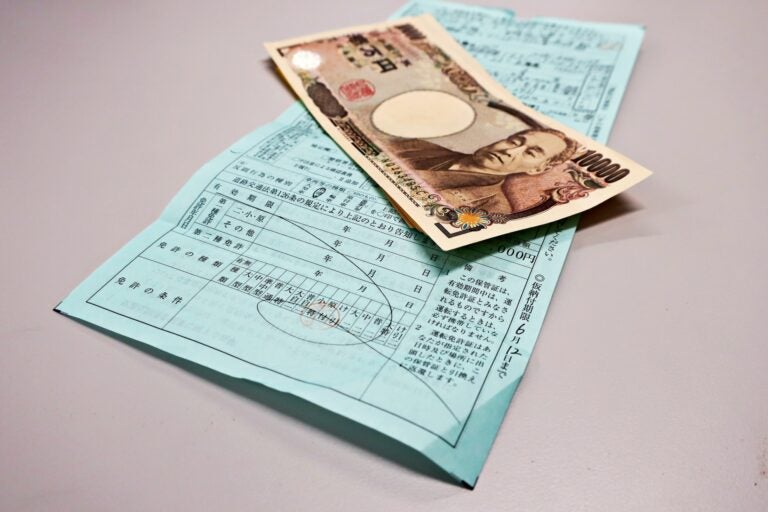自転車の交通ルール。横断歩道は走行していいの? ~弁護士に訊いてみた~【クルマと法律vol.10】
交通問題やクルマに関する相談について、法律の見地から分かりやすく解説する連載「クルマと法律」。今回は、自転車を運転しているときの交通ルール。自転車に乗ったまま、横断歩道を通行していいのかを弁護士・芳仲美恵子先生に聞きました。
この記事をシェア
「自転車に乗って走るとき、横断歩道を通行してもいいのでしょうか? そもそも歩道を通行してもいいのでしょうか?」
自転車は横断歩道を通行してもいい?
相談者:自転車で走行する場合、クルマと歩行者どちらの交通ルールに従えばいいか分からなくなるときがあります。自転車に乗ったまま横断歩道を通行してもいいのでしょうか。
芳仲弁護士:可能です。道路交通法(以下「道交法」という)上、自転車は「車道」走行が原則です。しかし、例外的に「歩道」走行が許されている自転車がそのまま「横断歩道」を走行して道路を横断することは、むしろ道交法が想定しているところといえましょう。
相談者:そうなのですね! 「車道」走行が原則なのに、例外的に「歩道」を走行できるのですか。ややこしいですね。
芳仲弁護士:全くその通りですね。普段の生活で多くの方が利用する自転車は、ほぼ、道交法施行規則9条の2の2以下で定められている「普通自転車(道交法63条の3)」だと思われます。そのため、ここでは「普通自転車」を単に「自転車」と呼んで話を進めたいと思います。
【普通自転車とは】
一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が下記の基準に適合する自転車で他の車両をけん引していないもの。
■車体の大きさ 長さ:190cm以内 幅:60cm以内
■車体の構造
・4輪以下であること
・側車をつけていないこと(補助輪は除く)
・運転者以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用乗車装置を除く)
・ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
相談者:自転車にも種類があるのですね。わかりました。
芳仲弁護士:まず、「車道」通行が原則であることについて説明します。道交法の規定で自転車は「軽車両」にあたり(第2条第1項第11号イ)、「軽車両」は「車両」にあたります(第2条第2項第8号)。つまり、道交法上において自転車は「車両」にあたります。自転車を押して歩いている者は「歩行者」として扱われますが(第2条第3項第2号)ここでは考えないことにしましょう。
相談者:わかりました。基本的に自転車は「車両」なのですね。
芳仲弁護士:はい。そして、「歩道」と「車道」の区別のある道路(以下「歩車道の区別のある道路」という)においては「車両」は、車道を通行しなければなりません(第17条第1項)。自転車も「車両」である以上、「車道」を通行しなければならないのが原則なのです。
相談者:そうなのですか! 知りませんでした。
芳仲弁護士:そうです。ただし、道交法上の例外として、「自転車横断帯」がある場所の付近で「自転車」が道路を横断しようとするときは、その「自転車横断帯」を通行しなければなりません(道交法63条の6)。その場合、自転車は「車道」は走行できません。もちろん付近に「横断歩道」があっても、そこを走行することはできません。
相談者:なるほど。「自転車横断帯」があるときは、自転車はとにかくそこを走らなければならないのですね。
芳仲弁護士:実態はともかく、道交法上はそう規定されています。ちなみに「横断歩道」と「自転車横断帯」は、道交法上で下記のように定義されています。
【横断歩道と自転車横断帯の定義】
横断歩道:道路標識等により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう(道交法2条1項4号)
自転車横断帯:道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう(道交法2条1項4号の2)
例外的に歩道通行可能な場合がある。

普通自転車および歩行者専用の標識。(c)U4 – stock.adobe.com
相談者:原則は「車道」通行といっても、都心では自転車が「歩道」を通行していいという道路標示がされていて、多くの自転車が「歩道」を走行しているのを見かけます。
芳仲弁護士:そうですね。子どもや高齢者などが街中で自転車に乗る場合など、自転車が「車道」を通行することはむしろ危険な場合もあります。よって、以下の(1)から(3)の場合には、例外として自転車も「歩道」を通行することが許されているのです(道交法63条の4)。
【自転車が例外的に歩道通行できる場合】
(1)道路標識等により普通自転車の歩道通行が可とされている場合
(2)当該自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき(道交法施行令26条、規則9条の2の3で、70歳以上の高齢者、一定の身体障害者等が定められている)。
(3)車道や交通の状況に照らして当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
相談者:確かに、このように例外的に歩道通行が許されている自転車が、交差点にさしかかれば、そのまま「横断歩道」を走行して道路を横断することが必要ですよね。
芳仲弁護士:そうなります。
横断歩道は歩道ではない!?

横断歩道の脇に設けられた自転車横断帯。(c)Hassyoudo – stock.adobe.com
相談者:つまり、「横断歩道」も「歩道」だから、例外的に「歩道」通行を許された自転車が通行できるということなのですね?
芳仲弁護士:いいえ、違います。実は、道交法上において「横断歩道」は「歩道」ではないのですよ。
相談者:横断歩道は歩道ではないとは、どういうことですか?
芳仲弁護士:道交法は、「歩道」と「車道」について以下のように定義しています。
【歩道と車道の定義】
歩道:歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう(道交法2条1項2号)
車道:車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう(道交法2条1項3号)
芳仲弁護士:つまり「車道」は、道路が道路標示で区画されていれば足ります。しかし「歩道」は、歩行者の通行の安全を確保するという趣旨から、縁石や柵(ガードレール)、その他の工作物で物理的に車両が簡単に出入りできないことが重要な要素となっているのです。単に道路鋲とかペイントによる塗装等によって区分されたに過ぎない「横断歩道」は、道交法上の「歩道」とはいえないのです。
相談者:なるほど。では、道交法上の「横断歩道」とはどういうものなのですか?
芳仲弁護士:道交法では「横断歩道」は以下のように定義されています。「横断歩道」は、車両と歩行者の通行が交錯する場所に設置されるものですから、歩行者の安全の観点からは「歩道」とは同視できないということでしょうね。
【横断歩道の定義】
横断歩道:道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう(道交法2条1項4号)
相談者:そう言われると確かに、「横断歩道」の上をクルマも通過しますね。
芳仲弁護士:ちなみに道交法10条2項1号も、歩行者は「車道」を横断するとき”以外”は「歩道」を通行しなければならないと定めています。裏を返せば、歩行者が「車道」を横断するときは「歩道」を通行しなくてもよいと定めている訳です。つまり、この規定も道交法が「横断歩道」を「歩道」ではないと捉えていることの表れといえると思います。
相談者:そうか、「横断歩道」は厳密には「歩道」ではないので、自転車も通行できるということですね。私は、「横断歩道」という呼び名からして、「歩道」の一種なので、原則として自転車は通行できないのだと思ってしまいました。
車道を通行しているときは、そのまま直進!

普通自転車専用通行帯。(c)Hassyoudo – stock.adobe.com
相談者:「横断歩道」が「歩道」ではないということは、自転車は「横断歩道」を自由に通行していいということなのでしょうか?
芳仲弁護士:「自由に」というのは無理でしょうね。確かに、道交法上、自転車は一義的に「横断歩道」を通行できないことにはなっていません。しかし例えば、「車道」を走行してきた自転車が、そのままのスピードで、突然、横断歩道を走行するというようなことは、事故を誘発しかねない危険な運転とみなされます。
相談者:それは危険ですね。
芳仲弁護士:はい。ちなみに道交法は、以下の通り、「交差点」をあくまで「車道」の交わる部分と定義しています。
【交差点の定義】
交差点:十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう(道交法2条1項5号)
つまり、多くの場合、「横断歩道」は道交法上の「交差点」の外にあることになります。そのため、「車道」を走行してきた自転車が交差点にさしかかって「横断歩道」を通行して道路を横断しようとすれば、いったん「車道」を左折するか路外に出る(歩道に上がる)必要があります。この場合、あらかじめ「車道」の左側端に寄って「徐行」することが必要です(道交法25条)。
相談者:「徐行」をしないと違反になってしまうのですね。
芳仲弁護士:その通りです。また、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、路外出入りのための左折等もできません(道交法25条の2)。よほど充分に安全に配慮して徐行運転しない限り、「車道」を走行してきた自転車がそのまま「横断歩道」を通行することは困難でしょう。
相談者:無理に「横断歩道」を渡らない方がいいのでしょうか?
芳仲弁護士:自転車は軽車両ですから、自転車に乗って「車道」を通行するときは車道左側端を走行することが必要です(道交法18条1項)。そして、車道左側端を走行してきた自転車が、交差点を直進しようとする場合、自転車横断帯が設けられていればそこを走行する必要があり、自転車横断帯がないときは、いたずらに進路変更することなく車道の左側端をそのまま、交差点の向こう側まで直進することが基本です。最近は、青色矢羽根のピクトグラムなど交差点内で自転車が走行すべき進路が路面標示されていますので、安心して交差点を通行することが可能になってきました。(青色矢羽根については、こちらの記事を参照)
相談者:わかりました。自転車に乗ったまま横断歩道を通行すること自体は禁止されていないが、あくまで例外的に歩道走行を許された自転車が歩道を走行してきて交差点を横断する場合が想定されている。横断歩道を横断する際には歩行者等の通行を妨げないように注意しなければならない。そして、原則どおり車道を通行して交差点を直進する場合は、車道の左側端を真っ直ぐに進むのが基本なのですね! 解説ありがとうございました。
———————————————————————————————————————
(公財)日弁連交通事故相談センターでは、電話による交通事故無料法律相談を実施しています。
TEL:0120-078325 平日10:00~16:30(第5週を除く水曜は19:00まで延長)
https://n-tacc.or.jp
———————————————————————————————————————